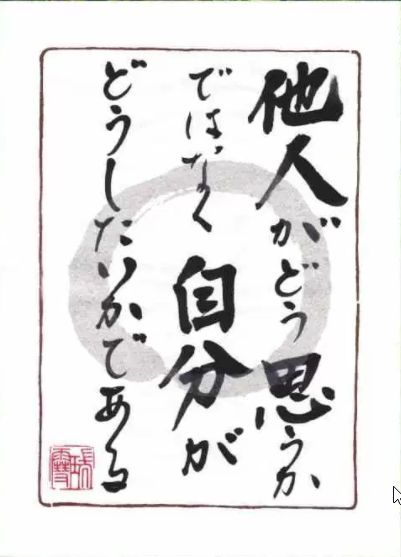【大阪スクール開校!】
宮森大地のすべてを伝える
大阪スクールの開校が決定しました
http://bit.ly/2qZiQLw
------------------------------
セラピストスキルアップ実践会認定講師の宮森大地です。
本日もブログにお越しいただき、本当にありがとうございます。
筋肉痛は学びになるな…と思います。
目的をもって運動をし、翌日にその目的に沿った部位が筋肉痛になっていると嬉しくなります。
違った部位が筋肉痛になっているとそれはそれで内観を見直すきっかけになります。
体を通して学べることが何より尊いですね…。
さて、本日は「過ぎたるは猶及ばざるが如し…深呼吸は危険?」というお話。

(深呼吸で画像検索するとたいていキレイなお姉さんが出てきます。
ストレス社会と言われ、交感神経が優位になっていると言われ、副交感神経を優位にしてストレスを軽減させる深呼吸は現代では特に体に良いとされています。
とは言え、過ぎたるは猶及ばざるが如しということで、深呼吸もやり過ぎると危険を伴います。
さて、懐かしの生理学の復習をしてみましょう。
皆さんの大好きな酸素解離曲線の登場です↓

苦手な人も冷静に図を見てみましょう…とりあえず正常な状態の青い実線を見てください。。
縦軸に酸化ヘモグロビンの割合(全ヘモグロビン中の酸素と結合しているヘモグロビン割合)、横軸に酸素分圧(酸素濃度)が書かれています。
このS字の曲線を簡単に説明すると、酸素濃度の高いところではヘモグロビンは酸素と結合しやすく、酸素濃度の低いところではヘモグロビンは酸素を手放しやすくなる(細胞に酸素を届ける)ということです。
なるほど、こういう性質があるから体の隅々まで酸素を届けることができるわけですね。
で、ここで注目したいのは赤い破線と緑色の破線の部分。
線の左右に何気なく書いてありますが、pH(水素イオン濃度)と温度(体温)、DPG濃度(解糖系の中間産物)が酸素解離曲線に影響を与えるようです。
これも分かりやすい赤い破線で説明しますが、上記の調整因子は代謝が良い組織(例えば運動時の骨格筋)で増加しますので、よりヘモグロビンが酸素を手放しやすくなるのです。
なるほど、こういう性質があるから酸素需要の高いところに優先的に酸素を届けることができるわけですね。
さて、ここで深呼吸に話を戻します。

血液はほぼ中性(pH7.35-7.45)でかなり厳密に調整されていますが、今回は呼吸の影響を考えていきます。
呼吸は吸息・止息・呼息を繰り返していきます。
この3つの割合で血液中の二酸化炭素濃度が変わってきます。
呼息(二酸化炭素の排出)と比較して、吸息および止息が優位になった場合はどんどん二酸化炭素濃度が高くなります。
二酸化炭素濃度が高まるとpHは低下しますので血液は酸性に傾き、酸素解離曲線で言うと赤い破線の方向にシフトします。
この時、体は重要な組織である脳などへの酸素供給を増やしますので、これがリラックスにつながるとされています。
しかし、二酸化炭素分圧が高まると排出を高めるために換気が亢進されますが、それを無視して深呼吸を続けるとどんどん体は酸性に傾いていきます(呼吸性アシドーシス)。
この場合、頭痛や錯乱、眠気が生じ、最悪は混迷や昏睡に至る場合もあります。
ということで、体の声を無視すると良いと思われることでもデメリットが生じることがあります。
科学的にも過ぎたるは猶及ばざるが如しは言えるのですね。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それでは、また明日。
◆認定インストラクターによる症例報告は以下からチェック!!(毎週日曜更新)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://bit.ly/2OXOGDb
◆セラピストスキルアップ実践会のブログ更新情報はコチラから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
◆こっそりやっている…宮森個人のLINE@はコチラ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
セラピストスキルアップ実践会認定講師
宮森大地